東京電力の調達品リストを見ていると、
『配電用変電所用変圧器 66/6kV 20MVA』なんていう項目がある。
機器の故障などに備えるなら
変圧器の台数は変電所あたり 少なくとも 2 台, おそらくは 3 台以上あるだろうが、
私には 10 台以上並んでいるようにも想像しがたいので、
きっとこの変圧器 3 〜 5 台分位が 典型的な配電用変電所のスケールなのだろう。
(というか、きっとそうなる様に 1 台の変圧器の容量を設計するだろうと思う。)
この 20 MVA 変圧器は、 定格電圧 6.9KV の三相交流を使っているため、
定格電流の一次側(入力)が 167 A で、 二次側(出力)では 1670 A となる。
定格であるから幾分余裕をみた数字の筈ではあるが、 それにしても凄い電流量だ。
どんな開閉器 (というより遮断器) を使っているのか 気になるところでもある。
また、配電線路への繋ぎの部分がどうなっているのか にも興味がそそられる。
一世帯の消費電力が 4kVA だと仮定すると、 5000 軒分だ。
う〜ん、 これだけでは多いのか少ないのか良く判らないな。
で、 世帯数を調べた所によると、 神奈川県の世帯数は 310 万だそうだ。
私の自宅のある川崎市麻生区の世帯数で 54 万。
ということは、 麻生区全体に変圧器が 100 台要るのか。
仮に変電所当たりの変圧器台数が 4 台だとすると、 変電所 25 箇所分。
結局、 電流量を数字で見るとたしかに凄いけれど、
電力需要の方がもっともっと凄いというのが結論。
という訳で、手始めに、最寄りの百合ヶ丘変電所へ行ってみた。 塀はなく、金網と植木程度だったので、少しは中の様子が伺えた。 なお、外から覗いていただけなので、 中の機器の機能などは全て私の想像である。 言ってみれば、この page は私の推理ゲームの途中経過であり、 このゲームの真実の解は決して得られないのである。 大きく外していなければ良いのだが。 (^^;;
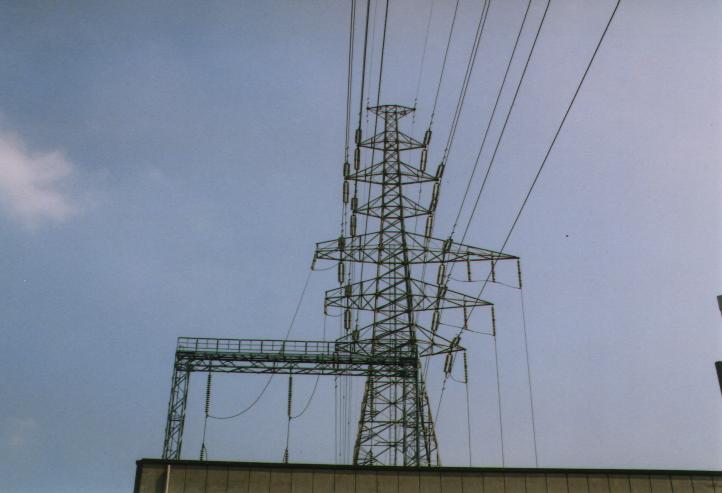 変電所とその背後の柿生線 18 号基
変電所とその背後の柿生線 18 号基
ここが変電所への電力の入口となる。
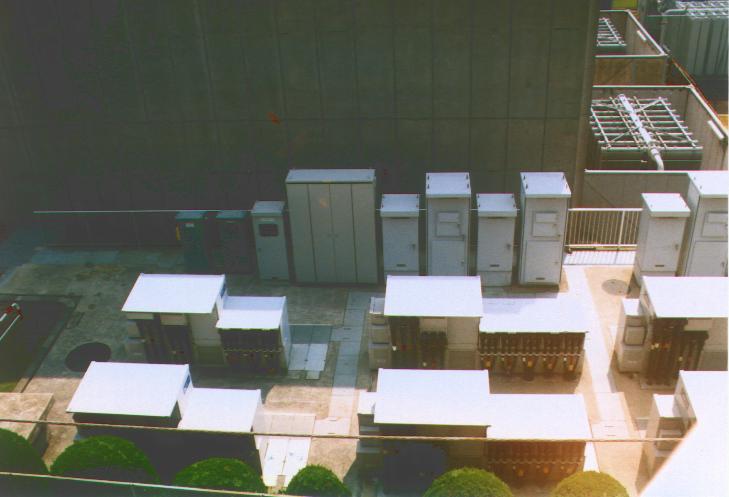 変電所敷地内のフィーダ用地下ケーブルヘッダ装置群
変電所敷地内のフィーダ用地下ケーブルヘッダ装置群
で、こちらが変電所からの電力の出口だ。なおこの装置の正式名称は良く判らない。
写真には写っていないが、横の所に『1BMC-A』なんて書いてある。
第一バンク (1B) の多接触継電器 (MC) の A 号基か????
私は多接触継電器というのが何を目的とした、 どんな継電器であるのか判らない。
書籍で出てきた表の中にあっただけで 名前でしか知らないのだが、
少なくともここは継電器が出てくる所ではないだろうと思う。
というのは、
遮断器を動作させるための信号を 生成したり合成したりするのが継電器だ、
と理解しているからだ。
だから、たとえば、
この装置の主目的が遮断器であったとしたなら、
まだ少しは私にも話が見える。
というより、配電線を保護する都合上、
一番最後はとんでもない異常電流が流れている時でも
安全に解放することのできる『遮断器』でないとマズイと思うのだ。
それでも、おそらく最初の 1B が第一バンクを指すと見るのは当たっているだろう。
もしもそうだとすると、 この変電所は三つのバンクから構成されており、
各バンクから 6 〜 9 本のケーブルが出ているように見える。
まぁ、納得できるスケールではある。
やはりバンク当たり 20 MVA なのだろうか。
もう一段階大きい変圧器の容量が 25 MVA か 30 MVA 位だったら、
そういった変圧器を使っている可能性もある。
右奥に見えているのは 変圧器の絶縁油の冷却器だろうか、 三つあるようだ。
しかし、 今年の暑さでは変圧器も辛かろう。 ちなみにこの日の最高気温 35 度。
 百合ヶ丘線 1 号基の鉄塔
百合ヶ丘線 1 号基の鉄塔
このガントリー型鉄塔は 柿生線から引き下ろした高圧送電線を
変電所建屋に取り付けられたブッシングに渡すために 建てられている。
世の中には、 電力会社の敷地の外に出る事もなく、
1 号基だけで終ってしまう送電線が 結構あるのかも知れない。
 フィーダ用地下ケーブルヘッダ装置, 右半分中心
フィーダ用地下ケーブルヘッダ装置, 右半分中心
この 1 台からは 3 本 1 set の配電フィーダ線が 4 set 出てきている。
各セットの上にある銘板には付近の地名などが書かれているので、
こちらが出力側であろうと推察される。
ケーブルの太さは手首ほどで、
余り捻ったような様子は見えないが、 場所からして、
325 mm2 または 500 mm2 の CVT ケーブルだろうか。
電力ケーブルの敷設条件にもよるが、
325 mm2 なら 600 A 程度の電流を流せるし、
500 mm2 なら 750 A 位を流せる。
フィーダ線の set 数は装置によって 3 〜 5 set と異なっている。
1 set のケーブルに巻かれたテープの色は、
左から順に白・赤・青, または白・赤・黒。
黒と青はどちらでもいいのであろうか、
あるいは退色して違う色に見えるようになっただけなのか…。
しかし、このケーブルの反対側の端、
地下フィーダ・ケーブルが地上に出てくる所はどうなっているのだろうか。
見てみたいものだ。 しかし、何処だろう? 探すか。 でも、どうやって?
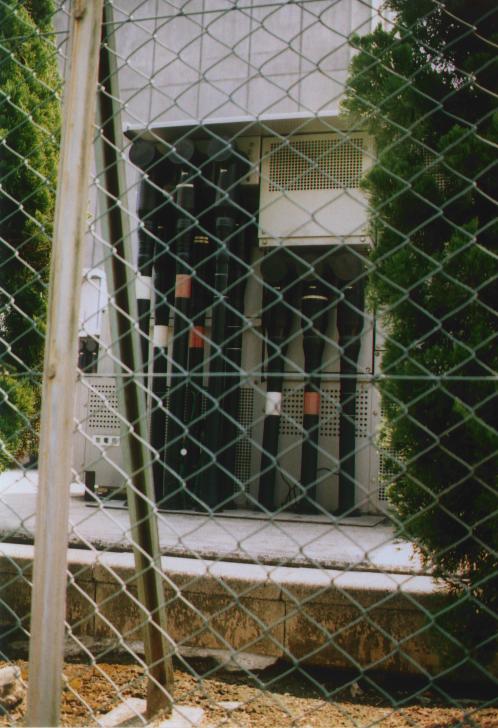 フィーダ用地下ケーブルヘッダ装置, 左半分
フィーダ用地下ケーブルヘッダ装置, 左半分
右半分が出力側のようだったので、こちらは入力側であろうか。
ケーブルは左端に前後で 2 set が、その右にもう 1 set がある。
何故何セットもあるのだろう。
自分本来のバンクに接続するケーブルと、
自分が接続しているバンクがトラブルを起こした時に使う、 渡り母線であろうか。
でもそんなものであれば、 こんな所から引き回さないで、
変電所建屋内の変圧器の直後に 三極断路器でもあれば充分だろう。
ただ単に、 電流量を稼ぐために、 並列に配線しているだけかも知れない。
1000 A 以上の電流が流れる部分であるし、
問題のケーブルと送出用のケーブルとが 大体同じ太さのように見えたから、
2 set や 3 set の並列ぐらいは 充分にありそうなことでもある。
左下のプレートには、 何の事かは判らないが、 『放電用』と書いてある。
してみると、 これらのケーブルのどれかの先には
コンデンサが付いていたりするのだろうか。
でも普通は、 需要家側が付けるもののような気もするし、
地下ケーブルはただでさえ キャパシタンスが大きいのだ。
わざわざ伝送距離を縮めるような事もするまい。
では話は逆で、 地下ケーブル自身に溜った電荷を放電するためなのだろうか?
あるいは、 この筺体内に停電時に開閉器を引きはずすための
スーパー・キャパシタでも入っているのだろうか。
 変電所敷地から出てきて電柱に取り付いた通信ケーブル
変電所敷地から出てきて電柱に取り付いた通信ケーブル
この写真を撮った時には、
卸したての電力がこの道を横切るケーブルを流れている筈だと信じて疑わなかった。
しかし、その割には、すぐに電柱のてっぺんに昇って行ったりはしていない。
では、この電柱のてっぺんの配電線はどこからフィードされているのか。
ここら辺から、少し怪しくなってきた。
ひょっとしたら、外から中に入ってくる線なのか?
例えば、変電所内の電源は、
自前とヨソからの 2 系統を使えるようにしているとか。
ここまで来ると、もう不安だ。
少なくとも最初の開閉器くらいまでは、この電線を追いかけていっておくのだった…。
この日、暑かったからなぁ。 # 単なる言い訳。
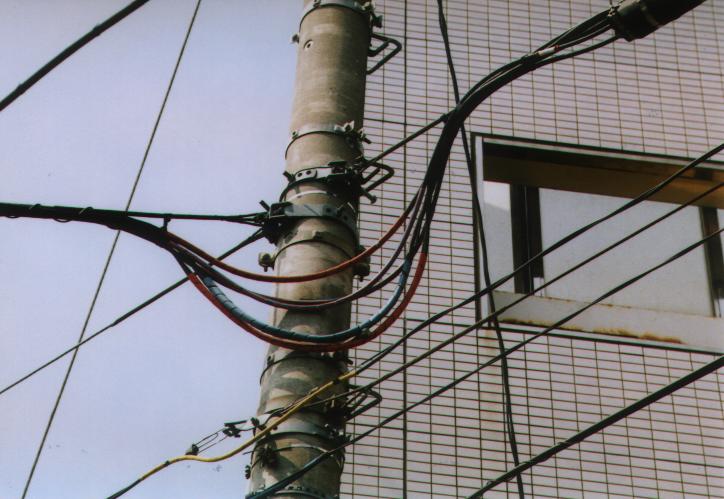 通信ケーブルの電柱への取り付き
通信ケーブルの電柱への取り付き
ケーブルが電柱のコンクリートと擦れて、
地絡 (地面とショートすること) しないようにカバーが付いている。
ケーブルは 5 本。
どうも、カメラを片手に現場にいると、
目に映るものに気を取られてしまう所為か、
充分に考察ができなくなってしまうようだ。
まぁ、 カメラ・バッグを肩から下げて町中をウロ付くなど、
廻りの視線が気になって、カメラをゆっくり構える事も難しいくらいだからだろうか。
いつも出来上がったプリントを見ながら、
あれもこれも見てくるべきだった、 とホゾを噛む事の繰り返しである。
また見に行かなければなるまい。